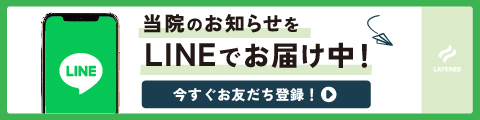医師紹介
院長
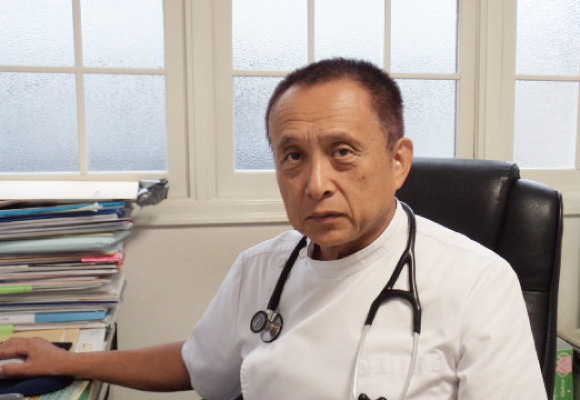
松葉 育郎
IKURO MATSUBA
当院は糖尿病や糖尿病予備軍(境界型)、その他生活習慣病を持つ患者様に、食事・運動療法を重視した診療を行っています。食べ過ぎや運動不足を改善せずに、薬で病気を抑えるのは根本的な解決にはならないからです。食事や運動習慣を少し変えるだけでも大きな効果があり、薬なしで過ごせる方や、インスリン注射をやめることが出来た方々も多くおられます。
普段の食事内容を詳しく聞き取り、また、運動内容を一緒に考え、個々に合わせた治療と改善方法を相談し、楽しみながら実施・継続・改善可能な計画を提案できるよう心がけています。
経歴
- 1954年 米国シカゴ生まれ。
- 東京慈恵会医科大学卒業。
- 東京慈恵会医科大学院医学博士課程を経て医学博士取得。
- Hagedorn研究所(デンマーク)研究員を経て、帰国後、東京慈恵会医科大学第3内科講師。
- 1991年 松葉医院を神奈川県川崎市にて開業。
所属学会・認定医等
- 日本糖尿病学会 専門医
- 日本内科学会 認定医
主な役職
【現職】
- 日本糖尿病学会名誉評議員
- 日本糖尿病協会関東支部理事
- 聖マリアンナ医科大学 臨床教授
- 神奈川県内科医学会学術部会長
- 神奈川県内科医学会糖尿病対策委員会委員長
- 神奈川県療養指導士認定機構療養指導委員会委員長
- 神奈川県糖尿病推進会議委員
- 糖尿病データマネージメント研究会(JDDM)臨床研究プロトコール委員
- 川崎糖尿病懇話会幹事
【歴任】
- 全国糖尿病医会理事、日本糖尿病協会委員、東京臨床糖尿病医会幹事
- 日本糖尿病協会季刊誌〈さかえ〉編集委員など
業績
【論文と学会発表・講演会】
PDFにてお読みください。
【メディア】
インタビュー記事です、ボタンからご覧ください。
【著書】
- 糖尿病を上手にコントロールする生活術―先輩患者さんの失敗・カン違いから学ぶ 2006年主婦の友社
- 高コレステロール・高中性脂肪を上手にコントロールする生活術―先輩患者さんの失敗・カン違いから学ぶ 2007年主婦の友社
- よくわかる血糖値を下げる基本の食事 2009年主婦の友社
- 血糖値を体型別治療でどんどん下げる 2017年技術評論社
副院長
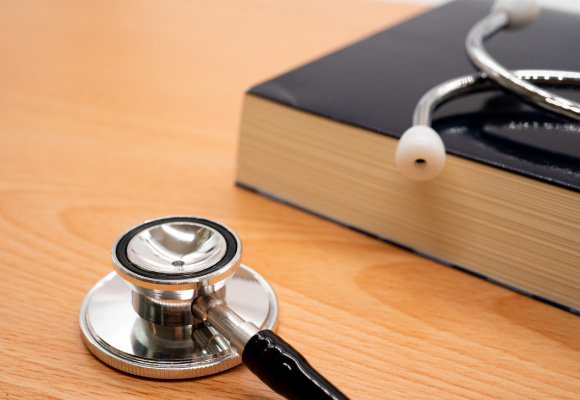
松葉 怜
REN MATSUBA
大学病院では、糖尿病を中心とし、高血圧、脂質異常症、高尿酸血症、肥満症などの生活習慣病、原発性アルドステロン症を主とした副腎疾患や甲状腺疾患、その他の稀な内分泌疾患を診療してきました。
多くの第一線で活躍する先輩医師から指導を受け、患者様の人生は自分の人生の一部でもあるということを学びました。患者様たちが、自身が病気であることを忘れ、また合併症(心筋梗塞、脳卒中、神経障害、網膜症、腎不全、足切断)などを心配せず気楽に楽しく毎日を過ごせるような医療を提供したいと考えています。
経歴
- 聖マリアンナ医科大学卒業
- 聖マリアンナ医科大学大学院博士課程(代謝内分泌:生活習慣病プロフェショナル養成課程)、理化学研究所横浜研修にて2型糖尿病感受性遺伝子領域の研究を経て聖マリアンナ医科大学助教
- 2019年聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院主任医長
難治性副腎疾患研究プロジェクトに参加し研鑽。 - 2022年現松葉医院副院長、聖マリアンナ医科大学代謝・内分泌内科非常勤講師
- 川崎糖尿病懇話会 幹事
- 川崎南部摂食嚥下・栄養研究会 幹事・世話人
所属学会・認定医等
- 日本糖尿病学会 専門医
- 日本内科学会 認定医
- 日本内分泌学会
- 米国内分泌学会(ENDOCRINE SOCIETY)
- 日本高血圧学会・日本甲状腺学会
- 緩和ケア研修会修了
- かかりつけ医認知症対応力向上研修修了
【著書】
部分執筆
- 内分泌画像検査・診断マニュアル, 第1版, 第5章 副腎および関連疾患 Subclinical Cushing症候群 副腎CT・MRI. 2020年 診断と治療社
- 最新ガイドラインに基づく代謝・内分泌疾患 診断基準 2021-’22, 第1版, 4. 副腎疾患 腫瘍 Cushing症候群(サブクリニカルを含む) 2021年 株式会社総合医学社
- Medicina, 褐色細胞腫, パラガングリオーマ 交感神経刺激症候のある高血圧を見逃さない! 2021年 医学書院
- 糖尿病・内分泌代謝科, 副腎性サブクリニカルCushing症候群. 2021年 科学評論社
医師
石井 賢治
【経歴、所属学会・認定医等】
- 東京慈恵医科大学卒業
- 日本内科学会認定内科医
- 日本糖尿病学会
- 日本医師会認定産業医
宮本 明
【経歴、所属学会・認定医等】
- 防衛医科大学卒業
- 総合高津中央病院
心臓血管センター顧問 - 日本内科学会認定内科医
- 日本内科学会総合内科専門医
- 日本循環器学会循環器専門医
- 日本心血管インターベンション治療
学会指導医,専門医,認定医・代議員 - 日本脈管学会専門医・評議員
久原 亮二
【経歴、所属学会・認定医等】
- 防衛医科大学卒業
- 総合高津中央病院
心臓血管センター部長 - 日本内科学会認定内科医
- 日本心血管インターベンション
治療学会認定医
担当医師
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前の部 9:00〜12:30 |
松葉 育郎 松葉 怜 |
松葉 育郎 松葉 怜 |
松葉 育郎 | 石井 賢治 ▲ |
松葉 育郎 松葉 怜 |
松葉 育郎 松葉 怜 |
| 午後の部 15:00〜18:00 |
松葉 育郎 松葉 怜 |
松葉 育郎 松葉 怜 |
松葉 育郎 ※循環器 |
ー |
松葉 育郎 松葉 怜 |
ー |
| 午前の部 9:00〜12:30 |
午後の部 15:00〜18:00 |
|
|---|---|---|
| 月 | 松葉 育郎 松葉 怜 |
松葉 育郎 松葉 怜 |
| 火 | 松葉 育郎 松葉 怜 |
松葉 育郎 松葉 怜 |
| 水 | 松葉 育郎 | 松葉 育郎 ※循環器 |
| 木 | 石井 賢治 ▲ |
ー |
| 金 | 松葉 育郎 松葉 怜 |
松葉 育郎 松葉 怜 |
| 土 | 松葉 育郎 松葉 怜 |
ー |
- 隔週水曜日午後は、循環器診療があります。
宮本 明 医師
久原 亮二 医師
▲ 毎週木曜日は、9:00~12:00までとなります。
・夏季、年末年始休診につきましては、「お知らせ」にてご確認ください。